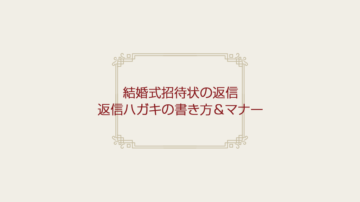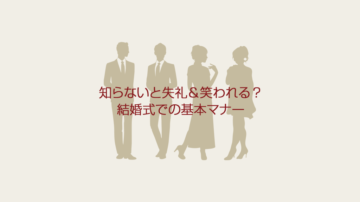最近は少人数での結婚式をおこなうカップルが増えています。
友人や会社関係者などは招待せず、親族のみでの結婚式を検討中の方もいらっしゃるのでは。
親族だけで結婚式をおこなう場合、
「親族ってどこまで呼ぶものなの?」
など、招待する範囲が気になりますよね。
『呼ばれた』『呼ばれなかった』など、後々面倒なことになったら大変です。
ということで今回は、親族のみの結婚式で気になる『招待する人の決め方』について解説。
『親族のみの結婚式』における、「誰を呼ぶ?」「ゲストをどうやって決める?」といったお悩みを解決します。
そもそも『親族』とは?
「親族をどこまで結婚式に招待するか」を考える前に、
「そもそも『親族』とは何か」
「『親族』とは誰を指すのか」
ということについて、簡単に解説します。
親族の範囲は民法で定められている
『親族』の範囲については、実は民法で定められています。
日本の民法は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を「親族」として定める(民法第725条)。
ちなみに上記に出てくる『血族(けつぞく)』とは、血の繋がりのある血縁関係のこと。
『姻族(いんぞく)』とは、配偶者の血族のことを指します。
『いとこ』を具体例に説明すると、
- あなたの『いとこ』は、4親等の血族なので『親族』である(6親等内の血族に該当)
- あなたの『いとこ』の配偶者は、4親等の姻族なので『親族』ではない
ということになります。
親族と親戚(親類)との違い
『親戚』と『親類』は同じ意味です。
しかし、『親族』と『親戚(親類)』には、
- 『親族』は先ほども紹介した民法で範囲が決まっている
- 『親戚(親類)』は範囲に決まりがなく、血縁関係・婚姻関係など繋がりのある人を指す言葉
といった違いがあります。
先ほど紹介した例で説明すると、
- あなたの『いとこ』の配偶者は、『親族』ではないが『親戚(親類)』
ということになります。
どこまで呼ぶ?招待する親族の決め方
親族のみの結婚式をおこなう場合、親族をどこまで呼ぶべきか悩むものです。
つづいては、結婚式に招待する親族の決め方について紹介します。
『親族』より『親戚』で考える
親族のみの結婚式とはいえ、招待する人を決める場合は『親族』より『親戚』で考えるのが良いでしょう。
『親族』の範囲としては『6親等内の血族』とありますが、さすがに曾祖父母ぐらいが現実的。
また法律上は『親族』の範囲外だとしても、いとこの配偶者とも仲良しだったら結婚式に招待したいですよね。
地域や両家の考え方、親戚付き合いの深さなども様々。
いろいろな面を考慮して招待する人を決めると良いでしょう。
決め方1.両親と相談して決める
1つめの方法は、『両親と相談』して考える決め方です。
新郎新婦だけで結婚式に招待する親族の範囲を決めるのは難しいもの。
『親族のみでおこなう結婚式』ということであれば尚更です。
まずはご両親に相談することが大切。
「この範囲まで招待すれば問題ない」
「この人は絶対に呼ばないといけない」
といった、親族間での決まり事があるかもしれません。
新郎新婦だけで勝手に決めてしまい、後々親戚付き合いが面倒になってしまったら大変。
特に『親族が多い』『親族間の付き合いが深い』といった場合は、必ずご両親の考えを確認することが重要です。
決め方2.結婚式の規模・希望人数で決める
2つめの方法は、『自分たちが考える結婚式の規模』から考える決め方。
「10人程度の本当に少ない人数での結婚式がしたい」
「20人から30人ぐらいでの結婚式が良いな」
など、先に結婚式の規模や希望人数をイメージし、招待する親族を決める方法です。
『新郎新婦の希望が一番』『親族間で特に決まり事がない』という場合にオススメ。
念のため、ご両親とも相談しつつ調整すると良いでしょう。
招待範囲の目安
結婚式の規模・希望人数での招待範囲の目安は以下のとおりです。
| 結婚式の規模・希望人数 | 親族の招待範囲 |
|---|---|
| ~10名 | 両親、兄弟姉妹、祖父母 |
| 10名~20名 | 両親、兄弟姉妹、祖父母、おじおば |
| 20名~30名 | 両親、兄弟姉妹、祖父母、おじおば、いとこ |
注意
両家親族の人数・バランスは様々ですので、あくまでも招待範囲の目安として参考にしてください。
まとめ
ということで今回は、親族のみの結婚式における『招待範囲の決め方』について解説しました。
2つの決め方を紹介しましたが、どちらの場合でも一度は必ずご両親に相談することが大切。
後々親戚付き合いがややこしくならないよう注意しましょう。
『親族』より『親戚』で考えるのがオススメ。
両家・親族間の考え方や親戚付き合いの深さ、仲良し度など、いろいろな面を考慮して招待する人を決めることがポイントですよ。